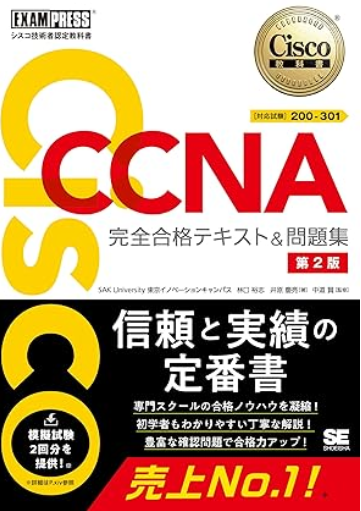こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。
「CCNAとLPIC/LinuCは、どっちを取ればいいの?」、「順番や難易度を知りたい」と考えるインフラエンジニア志望者は少なくありません。
結論から言うと、あなたが目指したいキャリアによって、選ぶべき資格や順番は大きく異なります。
この記事では、CCNAとLPIC/LinuCの違い、難易度、取得メリットなどを徹底比較しながら、ネットワーク・サーバー・クラウドそれぞれのキャリア別に、おすすめの資格取得順などを説明していきます。
未経験からインフラエンジニアを目指す方にもわかりやすく、また現場の声や、CCNAとLPICの両方を取得している私の経験を交えて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
結論:「CCNAとLPIC」は、目指したい将来のキャリアで選ぶべき
インフラエンジニアを目指す際に、多くの人が悩むのが「CCNAとLPIC、どちらを先に取得すべきか?」があります。
結論から言うと、どちらの資格を優先すべきかは「あなたが目指す将来のキャリア像」によって変わります。具体的に説明すると、以下の判断が最適です。
| 目指したいキャリア | 取得すべき資格の優先順位 |
| ネットワークに特化した仕事をしたい | CCNAが先 |
| サーバー・クラウドを扱いたい | LPICまたはLinuCが先 |
| インフラ全体に対応したい | 両方取得が理想的 |
ここでは、それぞれの資格の特徴と、どんなキャリアを志す人に向いているかをわかりやすく整理していきます。
ネットワークエンジニア志望なら「CCNA」から
CCNA(Cisco Certified Network Associate)は、ネットワーク技術に特化したベンダー資格です。ネットワークの基礎から、Ciscoルーター・スイッチの操作、セキュリティ、トラブルシューティングまでを体系的に学ぶことができます。
■CCNAを先に取得すべき人の特徴:
・将来、ネットワークエンジニアやセキュリティエンジニアを目指している
・Cisco機器が導入されている企業への就職・転職を狙っている
・ルーティング・スイッチングなどのインフラ通信領域に強みを持ちたい
CCNAの転職市場での評価
CCNAは、日本国内の多くのインフラ関連求人において「保有歓迎」または「必須条件」として記載されています。
実務未経験でも、CCNAレベルの知識を持っていることで、ネットワークの基礎力を証明できる材料となります。
ネットワークの道に進むと決めたなら、CCNA取得から内定獲得までの具体的な流れを、以下記事で確認しておきましょう。
→関連記事:ネットワークエンジニアになるには?未経験からの最短ルート
サーバー・クラウドエンジニア志望なら「LPIC/LinuC」から
LPIC(Linux Professional Institute Certification)やLinuC(Linux技術者認定試験)は、Linuxを中心としたサーバー・インフラ技術に関する資格です。
クラウド時代において、AWSやAzureの仮想マシンを扱う場面でも、Linuxの知識は不可欠です。そのため、サーバーエンジニアやクラウドエンジニアを目指す人にとって、LPIC/LinuCは非常に有効なスタートです。
■LPIC/LinuC を先に取得すべき人の特徴:
・Linuxを使ったサーバー構築・運用に興味がある
・クラウドインフラ(AWSなど)でキャリアを築きたい
・将来は「構築や自動化、IaC(Infrastructure as Code)」に進みたい
LPIC-1の転職市場での評価
実務未経験でも、LPIC-1レベルの知識を持っていることで、Linuxの基本操作ができる知識を証明することができます。
特にサーバー運用・クラウド基盤を扱う求人で「LPIC保有歓迎」が多く見られます。LPICやLinuCを取得することで、Linuxに強いエンジニアとしての証明になります。
サーバーやクラウドを主軸にしたいなら、Linuxスキルをどうキャリアに繋げるかが重要です。以下の関連記事が参考になります。
→関連記事:サーバーエンジニアになるには?未経験からの成功手順
インフラエンジニア志望なら「両方」取得がおすすめ
もしあなたが、ネットワークもサーバーも、そしてクラウドも広く浅く、最終的には深く学びたいと考えている「インフラエンジニア」を目指すなら、CCNAとLPIC/LinuCの両方を取得することを理想的です。
なぜ両方取得するのが理想的なのか?
インフラエンジニアとしての実力を示すなら、CCNA(ネットワーク)とLPIC(サーバー)を両方取得することは非常に有効です。CCNAとLPICを両方取得するメリットは、以下です。
■CCNAとLPICを両方取るメリット:
・トラブル対応力が大きく上がる(ネットワークかサーバーかの切り分けが早い)
・設計・構築フェーズで幅広く活躍できる
・クラウド転職でも即戦力として評価されやすい
インフラエンジニアの実務では、ネットワークとサーバーのトラブルが密接に絡み合って発生します。そのため、どちらの視点からも切り分けができるスキルセットは、チームの中で価値の高い存在になります。
例として、通信障害が起きた際に「ネットワーク由来か?サーバー側の設定か?」を素早く判断できる力は、運用現場では重宝されます。
また、設計・構築フェーズでも要件定義〜設計・構築までを一貫して対応できる人材として評価されやすく、特にクラウド案件では「幅広い知識が即戦力として見なされやすい」傾向があります。
当社が支援した多くのエンジニアも、この2資格を活かして年収アップやキャリアアップを実現しています。「クラウドや上流工程にも挑戦したい」方には、非常に強力な武器になる組み合わせです。
CCNAとLPICの概要を徹底比較、違いを一覧で解説
ITインフラ系のキャリアを目指す方にとって、「CCNAとLPIC、どっちを取ればいいの?」という悩みは非常に多いです。どちらも未経験者や初学者に人気の高いベンダー資格ですが、対応している技術領域や転職市場での評価は異なります。
ここでは、CCNAとLPICの違いを分かりやすく一覧で比較しながら解説します。あわせて、「自分はどちらから取得すべきか?」という視点も交え、ITインフラ業界で評価されるスキル選択のポイントをお伝えします。
CCNAとLPICの違いを一覧で比較
CCNAとLPICの違いを、表形式でまとめますので、まずは概要を比較してみましょう。
| CCNA | LPIC-1 | |
| 認定元 | Cisco(アメリカ) | LPI(Linux Professional Institute/カナダ) |
| 学習範囲 | ネットワーク全般(OSI、VLAN、ルーティングなど) | Linuxの基本操作、シェル、ユーザー管理、パーミッションなど |
| 対応分野 | ルーター・スイッチ設定、ネットワーク設計・運用 | サーバー構築・運用、Linux CLI操作、クラウド基盤にも応用可 |
| 難易度(ITSSレベル) | レベル2相当:やや易しい | レベル1相当(LPIC-1):易しい |
| 勉強時間の目安 | 180-250時間程度 | 120-150時間程度 |
| 受験料(税込) | 46,860円(1試験) | 16,500円×2科目(101・102)=33,000円 |
| 有効期限 | 3年間 | なし(有意性の期限は5年) |
| 試験形式 | CBT(選択式+ドラッグアンドドロップ+シミュレーション) | CBT(選択+記述/コマンド入力) |
| 日本語対応 | 可能 | 可能 |
| 転職市場での評価 | ネットワーク関連職で評価が高い | サーバー・クラウド系求人で評価されやすい |
■関連記事:CCNAとはどんな資格?試験の概要、内容などわかりやすく解説
■関連記事:【LPICまるわかり解説!】LPIC level1とは?試験内容や勉強、受験方法などを説明
ベンダー資格としての違い:CCNAとLPIC
CCNAとLPICはいずれもベンダー資格に分類されますが、次のような違いがあります。
■CCNA:
・Cisco社が認定する、Cisco機器を中心としたネットワーク技術に特化。
・ネットワークエンジニア、通信系企業で強みになる。
■LPIC:
・LPIという非営利団体が認定する、Linuxディストリビューション非依存の資格。
・サーバー・クラウド系エンジニアに向いており、最近ではLinuCも注目されている。
・正確に言うと、ベンダー資格ではなく、ベンダーニュートラル資格
どちらも「実務に直結する知識」を証明するという点で共通しています。一方で、インフラ分野の中でもカバーする領域が大きく異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
難易度と勉強時間の違い:ITSSレベルの目安も紹介
ITSS(ITスキル標準)レベルとは、日本の経済産業省が定義しているスキル指標です。企業が人材のスキルレベルを測る際の基準として用いられます。
| CCNA | LPIC-1 | |
| 難易度 | ITSSレベル2相当 | ITSSレベル1相当 |
| 内容 | ネットワークの構築運用や障害対応を行うレベル | 初級~中級レベルのサーバー運用業務に対応可能レベル |
| 合格率 | 公式非公表 | 公式非公表 |
| 勉強時間目安 | 未経験者で180-250時間程度 | 未経験者で120-150時間程度 |
| 学習スタイル | Ping-tや白本(参考書)を活用するのが定番 | Ping-t、白本(問題集)、あずき本(参考書)が人気 |
また、CCNAとLPIC-1の合格率は、公式非公表です。非公表であるものの、ITSSレベルや学習時間から、CCNAの方がLPIC-1よりもやや難易度が高いとされています。
あわせて、私の受験時の感想としても「LPIC-1より、CCNAの方が難しく感じました」。
■関連記事:【難しすぎる?】CCNAの難易度は?試験の内容や合格率とは?
■関連記事:【徹底解説】LPICの難易度は?レベル別で、他のIT資格と比較解説
受験料や有効期限の違いにも注意
資格取得を検討する上で、受験コストや更新制度も重要な比較ポイントです。
■CCNA:
・受験料:46,860円(税込)
・有効期限:3年(更新制)
・更新方法:再受験または上位資格取得(例:CCNP)
■LPIC:
・受験料:1科目16,500円(税込)×2(計33,000円)
・有効期限:なし(有意性期限は5年)
・更新方法:再受験または上位資格取得(例:LPIC-2)
注意点として、LPICの試験は、101試験と102試験の両方に合格して、初めて「LPIC-1取得」と認定されます。
転職市場での評価:CCNAはネットワーク系、LPICはサーバー・クラウド系で有利
■CCNAが評価される場面:
・ネットワーク監視・運用・構築
・SIerや通信キャリア系のプロジェクト
・「Cisco機器経験者歓迎」、「CCNA保有者優遇」の記載が多い
■LPICが評価される場面:
・サーバー構築・保守(特にLinuxベース)
・AWSやAzureなどクラウド基盤の設計・運用
・「Linux操作経験者歓迎」、「LPICまたはLinuC取得者歓迎」などが増加中
また、LPICやLinuCを保有しているとAWS SAA(ソリューションアーキテクト)などクラウド系資格との相性も良く、ステップアップ転職に有利です。
結論:目的に合った資格を戦略的に選ぶのがおすすめ
どちらの資格も基礎力の証明として有効な資格であり、履歴書や面接でのアピール材料になります。
一方で、「目的に合っていない資格」では、スキルと志望動機に一貫性が出ず、面接評価が伸びにくいこともあります。以下を参考に選択をすると、より適切に選ぶことができます。
| 目標とするキャリア | 最適な資格の選択 |
| ネットワーク構築・保守に関わりたい | CCNAが先 |
| Linuxサーバーやクラウド環境を扱いたい | LPICまたはLinuCが先 |
| インフラ全般に強くなりたい | 両方+AWSなどクラウド資格が理想的 |
資格選びで迷ったら、無料キャリア相談を
「どっちが自分に合っているのか、やっぱり分からない」、「資格を取ったあと、どんな求人があるのか知りたい」という方は、インフラエンジニア専門の転職支援サービスにご相談ください。
あなたのキャリアの希望にあわせた資格提案、学習アドバイス、未経験OKの求人なども説明しています。
CCNAを取得するメリット・デメリット
ネットワークエンジニアの登竜門として知られるCCNA(Cisco Certified Network Associate)は、インフラ系エンジニアを目指す未経験者・若手にとって、非常に人気のあるベンダー資格です。
しかし「本当に取るべき?」、「コスパはいいの?」と迷っている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、CCNAの試験範囲や転職での評価、メリットとデメリットを中立的に解説します。これから学習を始める方にとって、判断材料となる「リアルな情報」として、参考にしてください。
CCNAの具体的な試験範囲
CCNAは、Cisco社が認定する世界的に有名なネットワーク資格です。2020年の大幅改訂以降、現在は「200-301 CCNA」という1試験に統合され、ネットワークの基礎全般をカバーしています。
CCNAの試験範囲(主なセクション)
| セクション名 | 主な内容 |
| ネットワークの基礎 | OSI参照モデル、TCP/IP、IPアドレス、トラブルシューティングなど |
| ネットワークアクセス | スイッチング、VLAN、STPなど |
| IP接続 | ルーティング、ルーティングプロトコル(OSPFなど) |
| IPサービス | DHCP、NAT、DNSなど |
| セキュリティの基礎 | ACL、VPN、ファイアウォールの基礎知識 |
| 自動化とプログラマビリティ | SDN、REST API、Ansibleなど(基礎レベル) |
また、CCNAは定期的に内容の変更があります。最新のバージョンはCisco Systemsのサイトで確かめることがおすすめです。現在のバージョンは、CCNA Exam v1.1 (200-301)です。
Cisco Systems CCNA Exam v1.1 (200-301)
CCNAの勉強で得られる知識、転職市場での評価
CCNAを学習することで、単なる試験合格だけでなく実務でも役立つ知識が身につく点が最大の魅力です。以下は、実際にネットワーク構築・運用の現場で必要となる知識です。
■CCNA学習にて、得られる知識:
・ネットワーク構成の理解(OSI、IPルーティングなど)
・Cisco機器(ルーター・スイッチ)の設定コマンド
・ネットワーク障害のトラブルシューティング
・セキュリティ対策の基礎
・自動化技術の基礎理解(SDN、Ansibleなど)
また転職市場でも、CCNA保有者は以下のような求人で評価されやすくなります。
■CCNAの転職市場での評価:
・「CCNA歓迎」「ネットワーク知識必須」などのキーワードあり
・ネットワーク運用・保守エンジニア
・SIer、SES、データセンター運用企業
特に求人票で「歓迎」や「優遇」と記載されていれば、面接時に有利な評価が得られる可能性大です。未経験からインフラエンジニアを目指す上で、「努力の証明」として説得力がある資格ともいえます。
CCNA取得の注意点(受験料、有効期限)
CCNAはメリットだけでなく、CCNAには「注意しておきたいポイント(デメリット)」もあります。特に「受験料」、「有効期限」については、しっかりと理解した中で、学習を始めるべきです。
CCNAは受験料が高い
CCNAの受験料は、1試験で46,860円(税込)です。LPICやLinuC、AWSなど、他の資格と比べても高額です。
2回受験すると、10万円弱の出費となるため、複数回受験が必要な場合は、さらに費用負担が大きくなります。
CCNAは有効期限が3年と短め
CCNAの有効期限は3年です。CCNAを更新するためには、「再受験」または「上位資格(例:CCNP)」の取得が必要となります。
ゆえに、CCNAは定期的な知識更新が必要となるため、継続的な学習意欲が求められます。
CCNAを取得すべき人の特徴
CCNAの取得をおすすめしたいのは、以下のような方です。当てはまる人は、前向きにCCNAを検討するとよいでしょう。
| タイプ | 解説 |
| ネットワークエンジニア志望 | 設計・構築・保守の基礎力として不可欠な資格 |
| 転職活動でアピール材料がほしい | 実務経験がなくてもスキルの証明になる |
| CCNPなどの上位資格を目指したい | キャリアパスとして重要な土台資格 |
CCNAはネットワーク領域での基礎力を証明する実用的かつ世界的に認知された資格です。
試験範囲は広く、学習にはある程度の時間と費用が必要ですが、その分転職市場での評価は高く、キャリアの武器になることは間違いありません。
LPICを取得するメリット・デメリット
Linux技術者としてのスキルを証明できる資格として、「LPIC(Linux Professional Institute Certification)」は非常に有名です。特に、インフラエンジニアを目指す未経験者や若手エンジニアにとって、キャリアの入口となる存在です。
一方で、「LPICは意味ない?」、「LinuCとの違いがわからない」、「本当に転職で役立つの?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
ここでは、LPICの試験範囲、難易度、転職市場での価値、そしてLinuCとの違いなど注意点も含めて、メリットとデメリットを客観的に解説します。
LPICの具体的な試験範囲
LPICは、カナダの非営利団体「LPI(Linux Professional Institute)」が認定する国際的なベンダーニュートラル資格です。レベル1(LPIC-1)からレベル3(LPIC-3)まで存在し、インフラ系エンジニアの成長段階に合わせて取得が可能です。
LPIC-1の出題範囲(101試験・102試験)
LPIC-1試験は2つ(101試験、102試験)に分かれており、それぞれ60問・90分。選択式/記述式の併用形式です。主な出題範囲は以下です。
| 試験 | 主な内容 |
| 101試験 | Linuxシステムの構成、パーティション、ブートプロセス、コマンドライン操作 など |
| 102試験 | シェルスクリプト、ユーザー管理、ネットワーク設定、セキュリティ、X Window など |
LPIC-1試験の詳しい出題範囲を知りたい方は、LPI公式サイトの「LPIC-1 Exam 101 and 102 Objectives」から確認してください。
Ping-t や あずき本(Linux標準教科書)、模擬試験などを併用すれば、未経験者でも3ヶ月以内で合格が狙えます。
LPICの学習で得られる知識、転職市場での評価
LPICを学ぶことで、Linuxの基礎を体系的に学ぶことができます。LPIC-1で学べることは、具体的には以下です。
■LPIC-1学習にて、得られる知識:
・ファイル操作、パーミッション、ユーザー管理
・パーティション設定、マウント、起動プロセスの理解
・ネットワーク設定(IP、ルーティング)
・シェル・スクリプトでの自動化
・システムログ、プロセス管理、ジョブ制御
LPIC-1を学ぶことで、実務経験がなくても「基本的なLinux操作に対応できる人材」と証明できるのが大きな魅力です。
また転職市場でも、LPIC-1保有者は、以下のような求人で評価されやすくなります。
■LPIC-1の転職市場での評価:
・求人票に「LPIC/LinuC歓迎」、「Linux経験者優遇」と記載された案件で評価
・特に、運用・保守系のインフラエンジニア職の応募条件にマッチ
・未経験者でも「やる気・素養」を証明する材料になる
LPICは、日本国内のIT企業やSIer、データセンター運営会社(iDC事業者)などから広く評価されています。
また、クラウド時代においてもLinuxの知識は必須です。AWSやGCPの裏側にはLinuxが動いているため、将来的なキャリアにも活きる基礎力が身につきます。
LPIC取得の注意点(LinuCとの違いなど)
LinuCとLPICの違いに注意
日本国内でLinux資格といえば、「LPIC」と「LinuC」の2つがあります。
| LPIC | LinuC | |
| 認定元 | LPI(カナダ) | LPI-Japan(日本) |
| 試験範囲 | 共通(過去は同一内容) | 共通(現在も約9割は同じ) |
| 認知度 | グローバルで強い | 国内企業で強い |
| 問題文 | 英語原文を翻訳 | 最初から日本語で設計 |
どちらもLinux技術者の登竜門として有効ですが、別試験です。認定元が異なる点に注意しましょう。
再認定が必要(実質的な「有効期限」あり)
LPICやLinuCには形式上の有効期限はありませんが、「有意性期限(Validity)」が5年と定められています。
取得後5年を過ぎると、ステータスが「ACTIVE(有意性あり)」から、「INACTIVE(有意性なし)」となり、上位試験の受験ができなくなります。また実質上の認定価値も下がってしますため、実質的な有効期限とも言えます。
Linuxを実務で使わないと定着しにくい
資格試験の勉強だけで終わってしまうと、知識が定着しない可能性もあります。
運用・保守や構築業務に実際に携わることがベストではあるものの、実務で使うことが難しい場合は、自分のPC上に仮想化ソフト(VirtualBoxなど)をインストールし、その中でLinuxを立て、操作することがおすすめです。
LPICを取得すべき人の特徴
LPICの取得をおすすめしたいのは、以下のような方です。当てはまる人は、前向きにLPICやLinuCを検討するとよいでしょう。
| タイプ | 理由 |
| 未経験からインフラエンジニアを目指している | スキルの証明として採用側に伝わりやすい |
| Linuxを使った業務に関わる予定がある | 基礎から体系的に理解でき、現場で役立つ |
| クラウドエンジニアを目指す人 | AWSなどでもLinuxの理解は必須 |
| 転職活動で資格を武器にしたい人 | 学習コストが低く、短期間で取得可 |
LPICやLinuCは、Linux技術者としての登竜門となるベンダーニュートラル資格であり、未経験からでも十分にチャレンジ可能です。またインフラエンジニアとしてのキャリア構築において、強力な武器になります。
ただし、LinuCとの違いや再認定制度、学習後の定着などに注意が必要です。「資格取得だけで終わらない」ことを意識しながら、実務へのステップとして活用していきましょう。
CCNAとLPIC、どちらを取るべき?目的別の具体的なロードマップ
「インフラエンジニアを目指したいけど、CCNAとLPICのどちらから勉強するべきかわからない」と悩む方は非常に多いです。
特に、未経験や若手エンジニアにとっては、最初の選択が今後のキャリアにも関わってきます。この記事では、「目指すキャリア」別に、最適な資格の順番と学習ステップを具体的に解説します。
パターン1:サーバー・Linuxの基礎から固めるロードマップ
■サーバー・Linuxの基礎から固めるロードマップは、こんな人におすすめ:
・将来的にクラウドエンジニアやサーバー構築を担当したい
・Linuxを扱う業務(運用・保守、構築)に興味がある
・クラウド資格(AWS)にも興味があるが、まずは基礎を固めたい
ステップ①:LPIC-1(またはLinuC-1)から始める
Linuxのファイル操作、権限設定、サービス管理などの基本を体系的に学べるLPICは、サーバー分野への第一歩です。
■LPIC-1(またはLinuC-1)の学習例:
・学習期間目安:1〜3ヶ月(未経験なら約120〜150時間)
・使用教材:Ping-t、あずき本(Linux標準教科書)、白本(スピードマスター問題集)
・目標:101、102試験の合格(LPIC-1取得)
ステップ②:CCNAでネットワークの基本を身につける
サーバー構築やクラウド設計に進むには、ネットワークの知識も欠かせません。CCNAでは、ルーティング・スイッチング、IPアドレス、VLANなどの知識を習得できます。
■CCNAでネットワークの基本の学び方:
・学習期間目安:2〜6ヶ月(未経験なら約180〜250時間)
・使用教材:Ping-t、白本(シスコ技術者認定教科書)、Cisco Packet Tracer
・目標:200-301試験の合格(CCNA取得)
ステップ③:AWS認定(CLF or SAA)でクラウドへステップアップ
サーバーやネットワークの基礎があれば、クラウド(AWS)の概念も理解しやすくなります。LPIC・CCNA → AWSの順は、クラウドエンジニアへの鉄板ルートです。
パターン2:ネットワークに強いインフラエンジニアを目指すロードマップ
■ネットワークに強いインフラエンジニアを目指すロードマップは、こんな人におすすめ:
・ネットワーク設計・構築を専門にしたい
・CCNAの分野に強い興味がある
・将来的にSIer、通信キャリア、ネットワーク機器ベンダーを目指したい
ステップ①:CCNAから始める
ネットワーク構成、ルーティング、セキュリティなどの基本を学ぶには、まずCCNAからのスタートがおすすめです。具体的な理由としては、以下です。
■ネットワークならCCNAを学ぶ理由:
・ネットワークの可視化や構築手順がしっかり学べる
・Packet Tracerなどで「手を動かす学習」ができる
・クラウド領域でもネットワーク設計の知識は必須
ステップ②:LPICをプラスして、Linuxの理解を補完
CCNAでネットワーク知識を得た後、Linuxも扱えるとインフラ全体を見れるようになります。
運用保守やトラブル対応の現場では、サーバー・ネットワーク両方の知識が求められるため、LPICの取得は大きなアドバンテージです。
ステップ③:上位資格やクラウドなどで専門性を高める
CCNAとLPICで基礎を固めたあとは、より上位の資格やクラウドへ展開することで、キャリアの選択肢が大きく広がります。
CCNAの上位資格を目指すなら、CCNPです。CCNAで得た知識をベースに、より大規模なネットワークの設計・構築スキルを証明できます。
クラウド分野での専門性を付けていくなら、AWS認定です。CCNAで学んだネットワーク知識を、AWSクラウド環境に応用する専門性を身につけられます。
パターン3:インフラ全般を学びたい場合のロードマップ
■インフラ全般を学ぶロードマップは、こんな人におすすめ:
・汎用的に活躍できるインフラエンジニアを目指したい
・未経験からエンジニアを目指しており、まずは地盤を作りたい
・さまざまな技術を学びながら、興味があるキャリアを見つけていきたい
ステップ①:LPICとCCNAを学習(おすすめ順はLPIC → CCNA)
LPICとCCNAを両方一緒に学習することは不可能ではありませんが、学習ボリュームや難易度を考えると、負担が大きくなりがちです。現実的にはLPIC → CCNAの順番がおすすめです。
まずはLPICで、Linux環境における基本的なコマンド操作(CLI)、ユーザー管理、ログの確認方法など、サーバー運用の土台となる知識を身につけましょう。
その上で、CCNAの学習を通じて、ネットワーク接続や通信プロトコル、IPアドレスの仕組みなど、インフラに欠かせないネットワークの理解を深めていくと、スムーズに実務スキルがつながります。
LPICとCCNAを順に習得すれば、インフラ業務の8割以上に関する基礎知識が身につくと言っても過言ではありません。未経験からインフラエンジニアを目指す方には、最適なスタートラインです。
ステップ②:実務もしくは、クラウド学習に進む
インフラ全般を理解したら、実務を通じて知識を定着させることが重要です。また、クラウド(AWS/Azure)や監視ツール、スクリプト(Bash/Python)などへの展開もスムーズです。
【比較】3つの学習パターンのまとめ
いままで説明した3つの学習パターンをまとめると、以下となります。
| パターン | スタート資格 | 目標 | 特徴 |
| パターン1 | LPIC → CCNA | AWSなどのクラウド資格 | サーバー・クラウドに強くなる王道ルート |
| パターン2 | CCNA → LPIC | CCNPなどの上級ネットワーク資格 | 通信系・ネットワーク設計に強み |
| パターン3 | LPIC → CCNA | 実務 or AWS/Azureへ応用 | 幅広いインフラ知識を身につけたい方向け |
上記のように、LPICとCCNAのどちらを先に取るかは、「目指すインフラエンジニア像」によっておすすめが変わりますが、大切なのは、資格の取得がゴールではなく「その後のキャリアにどう活かすか」です。
資格を取る順番が決まったら、次は「インフラエンジニア」としての全体像を、以下の記事で把握しましょう。どのルートを選んでも共通して必要な「未経験からの転職戦略」をまとめています。
→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?失敗しないロードマップ
また、資格取得を効率的に進め、転職やキャリアアップに繋げたい方は、当社のインフラエンジニア特化の転職支援サービスをご活用ください。無料相談を実施中です。
【2025】資格取得に役立つおすすめの学習方法と教材
インフラエンジニアを目指す上で、CCNAやLPICは、実務に直結するスキルを体系的に学べる資格です。
これらの資格は独学での取得も可能ではあるものの、効率的な学習法と、信頼できる教材の選定が合格の鍵になります。
ここでは、2025年時点で「最も評価が高い教材」、「最新の試験傾向に対応した学習サイト」、「初心者にやさしい講座」などを厳選して紹介します。
CCNAのおすすめ教材(書籍、オンライン講座、学習サイト)
書籍:白本(シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集)
シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301 第2版
まずは多くの合格者から指示される、CCNAの定番教科書である白本です。最新バージョンである200-301完全対応に対応しており、図解が豊富で初心者にもわかりやすく、演習問題で学習もできます。
■関連記事:【2025】初心者でも合格!CCNAのおすすめ参考書、問題集
オンライン講座:Youtube チャンネル(まさるの勉強部屋)
まさるの勉強部屋のCCNA試験対策は、CCNAに関する解説が豊富であり、初心者でも理解しやすい内容になっています。
また、単なる座学のみでなく、コマンド入力や、ネットワーク設定の手順を丁寧に解説しているため、有料級の動画を無料で見て、学習することができます。
■関連記事:【2025】CCNAのおすすめ勉強サイトを、無料・有料別で解説
学習サイト:Ping-t



CCNAの定番Web問題集であるPing-tは、非常におすすめできる学習サイトです。CCNAだけで約1,400問ほどの問題が掲載されており、また非常に丁寧な解説が有用です。
問題演習→解説→弱点克服の反復学習に最適であり、また復習や学習の履歴管理もできるため、CCNA合格者の多くが利用しています。演習中心の学習では、Ping-tと言えるでしょう。
■関連記事:【初心者、未経験者、独学可】CCNAのおすすめ勉強方法
LPIC-1のおすすめ教材(書籍、オンライン講座、学習サイト)
書籍:あずき本(Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応)



Amazon:Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応
あずき本(Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応)は初心者からのスタートに最適です。解説も比較的やさしく、学習理解をサポートする構成になっています。
また、LPIC-1の101・102試験の両試験に完全対応しており、基礎知識から実務寄りの内容まで網羅されています。
■関連記事:【独学で合格!】LPICのおすすめ参考書、問題集をレベル別で解説
オンライン講座:Youtube チャンネル(LPI 日本支部公式)



【公式】Linux Professional Institute 日本支部 LPI
オンライン講座では、LPIC資格認定元である、LPI(Linux Professional Institute)の日本支部公式チャンネルがあります。
公式チャンネルなので、勉強内容のみならず、試験の最新情報、バージョンアップに関する情報、ウェビナーのアーカイブなど、常に最新かつ正確な情報が手に入ります。
■関連記事:【勉強サイトだけで合格】LPIC level1のおすすめ勉強サイト有料・無料を解説
学習サイト:Ping-t



Ping-tは、CCNAのみでなく、LPICやLinuCにおいても定番であり、王道といえるWeb問題集です。LPICにおいても、解説が充実しており、解説を読むだけも理解が深まっていきます。
LPIC学習時でも、Ping-tはぜひ使うべき学習サイトです。また正答率管理ができるので、学習の進捗状況を可視化することもできます。
■関連記事:【独学でも合格!】LPIC level1の効率的な勉強方法、参考書、勉強時間などを説明
まとめ:正しい教材選びが、合格への最短ルート
資格学習において、「何を使って学ぶか」は非常に重要です。
LPICであれば、「あずき本」+「Ping-t」は王道学習であり、CCNAであれば「白本」+「Ping-t」+「Packet Tracer」が王道です。また、最新の試験傾向に合った教材を選べば、独学でも合格は可能です。
2025年以降も、インフラエンジニア市場は成長を続けています。資格取得を通じて、自信を持って次のキャリアステップに進んでいきましょう。
結論:迷ったらLPICから!資格を活かしてキャリアを築こう
インフラエンジニアを目指す上では、「CCNA」、「LPIC(またはLinuC)」、「AWS認定」など、さまざまな資格が候補となります。
それぞれに特徴や強みがありますが、どれから取得すべきか迷ったら、まずは「LPIC level1」からのスタートをおすすめします。
なぜ「LPICから」がベストなのか?
「LPIC level1」からのスタートをおすすめをする理由は、以下です。
■迷った場合、LPIC-1から始めた方がよい理由:
・Linuxの基礎は、どんなインフラキャリアでも必要になる
・CCNAやAWS認定よりも、学習負荷が比較的低い
・Ping-tや公式教材など、優れた教材が豊富
まず、Linuxの基礎は、どんなインフラ業界におけるキャリアでも必要です。AWSや仮想サーバー、クラウド運用にもLinux知識が不可欠であり、Linuxの基礎を学ぶことは損にはなりません。むしろ有用です。
また、LPIC-1は、CCNAやAWS認定よりも、初心者でも取り組みやすく、学習負荷が比較的低いです。初心者は、学習負荷が低い所からスタートし、「最初の成功体験を作る」ことも大事です。
さらに、Ping-tや公式教材など、学習を行いやすい教材がそろっているため、独学でも合格を目指しやすい環境が整っています。
LPICは、「サーバーを触ったことがない人」が「インフラの入り口に立つための第一歩」に適した資格です。
資格取得は、ゴールではなくキャリアのスタートライン
ただし、資格を取ること自体がゴールではありません。それをどう活かして、どうキャリアにつなげるかが重要です。
例として、LPIC+CCNAの取得で「運用・保守」から「構築・設計」へステップアップを行うことや、AWS認定と組み合わせて「クラウドエンジニア」へキャリアを広げていくことも有効です。
複数資格の取得により、転職市場での評価が大きく変わります。また資格は、未経験からの強い武器にもなります。だからこそ、学習と並行してキャリアの方向性を明確にすることが大切です。
未経験からインフラエンジニアを目指す場合の、資格・実務・転職まで含めたロードマップは、以下の記事で整理しています。
→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?失敗しないロードマップを見る
今すぐ動き出したい方へ:無料で支援を受ける選択肢
「一人で勉強を続けられるか不安」、「資格を取っても、転職できるか不安」、「どれを取ればよいか、決めきれない」といった悩みを持つ方は、インフラエンジニア専門の転職支援サービスで相談するのも一つの方法です。
「学習」と「キャリア」の両方を今すぐ相談でき、最初の一歩を進めるようになるかも知れません。
未来は、これからの一歩で変えられる
資格を取ることは、決して簡単ではありません。でも、正しい順番で、正しい教材を使い、正しい支援を受ければ、未経験からでもインフラエンジニアになることは十分可能です。
「いつかやろう」と思っているうちに、半年、1年と過ぎてしまうかもしれません。だからこそ、迷った今こそが、動き出すタイミングです。
今から、キャリアにつながる一歩を踏み出してみませんか?お気軽に「無料キャリア相談・転職支援サービス」にてご相談をください。
■無料キャリア相談・転職支援サービスに申し込む


■CCNA・LPICの無料資格取得支援、転職支援サービスを希望の方はお申込みはこちら