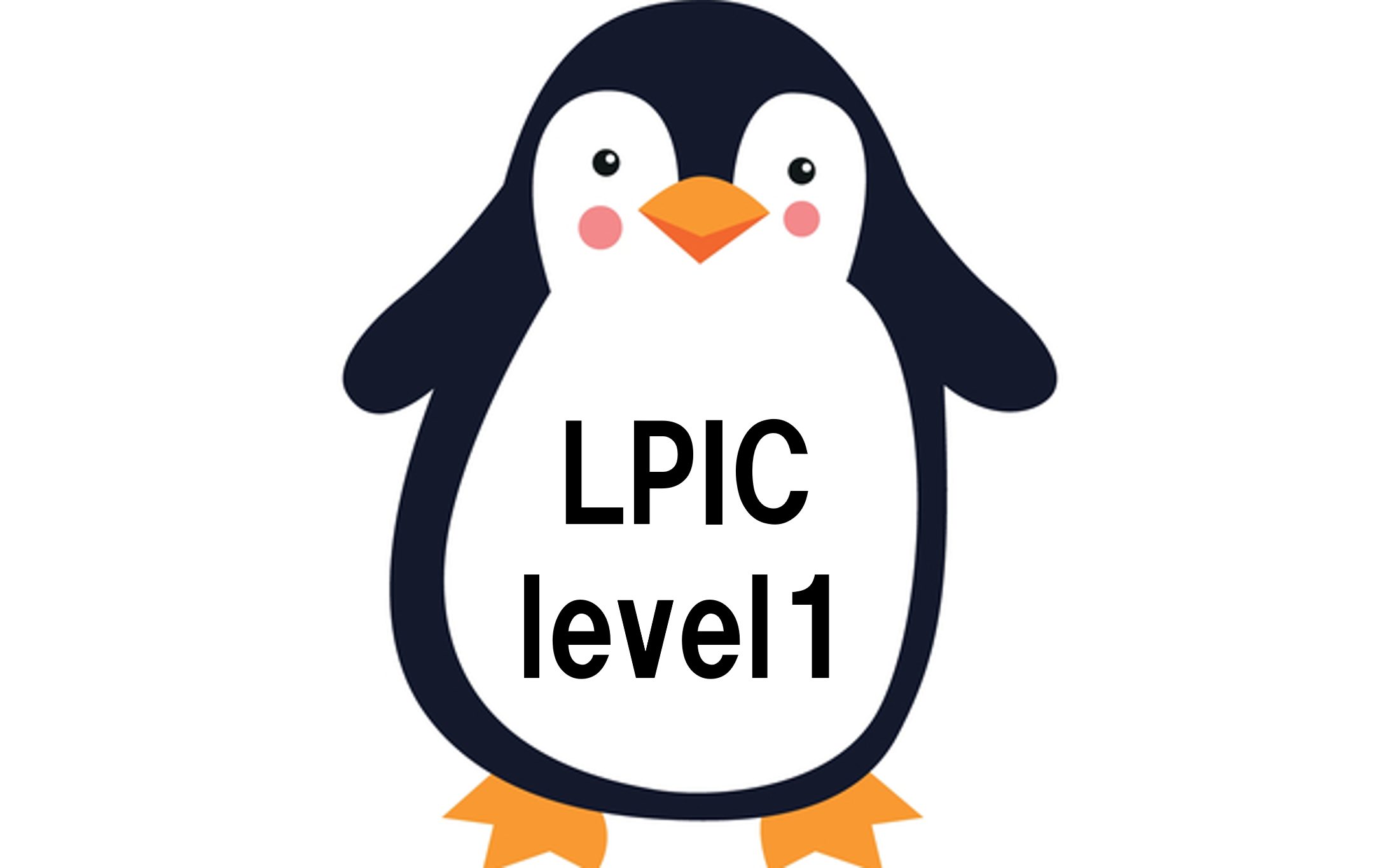こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。
「LPIC-1の勉強方法が知りたいけど、何から始めるべきか迷う、、」
「効率的に進めるやり方がわからない、、」
「独学で本当に合格できるのか不安、、」
そんな悩みを抱えていませんか?
実際にLPIC-1は出題範囲が広いため、最初の一歩でつまずきやすい資格でもあります。
特に101試験は、Linuxの基本操作やコマンドなど「最初に覚えることが多い分野」なので、多くの受験者が苦戦するポイントです。
でも大丈夫です。LPIC-1は、Linuxの基礎を体系的に学べる資格で、未経験からでも独学で合格を十分に狙えます。
実際、学習時間の目安は130〜180時間程度。大切なのは「正しい順序で」、「無理のない方法で」学習を進めることです。
この記事では、LPIC-1合格を目指す方に向けて、効率的で無駄のない学習方法を徹底解説します。さらに、資格を「キャリアアップにつなげたい方」には、無料キャリア相談のご案内もしています。
また、「独学に自信がない」、「教材費用を抑えたい」方は、【経済産業省採択】の無料リスキリングプログラムもぜひご確認ください。
【費用0円でLPICに挑戦】無料リスキリング転職の詳細を見る
LPIC-1は簡単ではない。でも独学で合格できる理由
LPIC-1は、Linuxの基礎知識を幅広く問う資格です。出題範囲はシステムの仕組みからコマンド操作、ネットワークやセキュリティまで多岐にわたり、決して「簡単な資格」ではありません。
それでも独学で合格できる人が多いのは、理由があります。
■LPIC-1の独学合格が可能な理由:
・出題範囲(シラバス)が明確に公開されている
・定番教材があり、独学ルートが確立されている
・合格基準は約65%、問題は選択式中心で攻略しやすい
出題範囲(シラバス)が明確に公開されている
LPICの試験はすべて 公式シラバス(試験範囲) に沿って出題されます。
信頼性が高い勉強サイトや問題集を使うことで、試験範囲に沿った学習が可能になり、より効率的な試験対策ができます。これにより、独学でも効率よく学習が進められます。
定番教材があり、独学ルートが確立されている
LPIC-1には、多くの受験者が使う 参考書・問題集・Ping-t・白本(スピードマスター問題集) といった定番教材があります。
この「王道ルート」を順番にこなせば、独学でも効率的に合格ラインに届きやすいです。
合格基準は約65%、問題は選択式中心で攻略しやすい
LPIC-1の合格ラインは 800点満点中500点(約65%以上の正答率)です。
満点を取る必要はなく、基礎を押さえれば合格可能です。また問題形式は、おおよそ8〜9割が選択式で、シラバスに沿った内容が出題されるため、対策を進めれば現実的に突破できます。
ちなみに、LPIは公式な合格率を公表していませんが、一般的には 50〜60%程度 と言われています。
難関資格のように合格率1桁ということはなく、正しく学べば誰でも挑戦できる資格 です。
LPICについて、詳しく知りたい方はこちら → 「【まとめ】LPICとは」、「【まとめ】LPIC-1とは」
LPIC-1合格に必要な勉強の流れ【教材3ステップ付き】
LPIC-1は出題範囲が広いため、学習の順序を間違えると効率が悪くなり、挫折につながります。
まずは「全体の流れ」を理解し、それを具体的な教材に落とし込むことで、最短ルートで合格を目指せます。
学習ステップの全体像(基礎 → 教材 → 問題演習 → 手を動かす)
LPIC-1の勉強は、次の流れで進めるのが効率的です。
■効率的な学習ステップ:
1. 基礎知識を理解する(Linux教科書=あずき本でインプット)
2. 教材学習を進める(Ping-tや問題集で知識を確認)
3. 問題演習で反復する(間違えを復習し、定着させる)
4. 手を動かして理解する
→まずは ノートにコマンドを書いて整理する
→次に エミュレータ(例:Web上のLinux環境) を触ってみる
→余裕があれば VirtualBoxなどで仮想環境を構築して試す
ポイントは、最初から完璧を目指さず、段階的に進めることです。
最初からVirtualBoxを作る必要はなく、まずはPing-tと白本で知識を固めれば十分に合格可能です。
ステップ1:インプット(あずき本)

Amazon:Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応
まず基礎を固めるために必須なのが、通称「あずき本」と呼ばれる 『Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応』 です。
■あずき本の特徴:
・LPI公式シラバスに沿った構成
・Linux初心者でも、やや理解しやすい解説
・模擬試験や直前チェックシート付き
あずき本は、最初から細かく理解しようとする必要はありません。
まずは 全体を2周程度読み流し、「なんとなく分かる」状態を作る ことが大切です。その後の演習(アウトプット)で理解が深まるので、ここで完璧を目指さないのがポイントです。
ステップ2:アウトプット(Ping-t、シラバス併用)



知識を定着させるアウトプット工程で、もっとも重要なのが Ping-t です。LPIC-1合格者の多くが利用しており、独学者にとっては「必須教材」といえるでしょう。
■独学なら、公式シラバスとの併用が効率的:
・スクールや講座を利用している場合は、カリキュラム自体が公式シラバスをカバーしているので、その流れに沿って学習すれば十分です。
・一方で独学の場合、シラバスを見ずにPing-tだけを進めると「試験に出ない問題に時間をかける」、「重要分野を落とす」といった非効率に陥りがちです。
そのため独学者こそ、公式シラバスを確認しながらPing-tを使うことが、合格への最短ルートになります。
Ping-tの特徴とメリット
多くの合格者が「Ping-tで8~9割以上解けるようになったら本番へ」を目安にしており、独学合格の王道教材といえます。
■Ping-tの特徴とメリット:
・問題数が豊富:LPIC101試験で約700問、102試験で約650問、合計1,300問以上
・解説が丁寧:ただ正解・不正解を確認するだけでなく、理解不足を補強できる
・苦手克服に最適:間違えた問題や苦手分野をソートできるため、効率的に復習できる
Ping-tの問題数はとても多いですが、全部完璧にできなくても合格可能です。「よく出る問題」に集中することが大事です。
Ping-t 活用のポイント
シラバスと照らし合わせて効率化
Ping-tは問題数が多いため、試験に出ない問題に時間をかけすぎることがあります。そこで重要なのが 公式シラバス との照合です。
■公式シラバスとの照らし合わせ:
・公式シラバスに載っているか確認する
・総重量(重要度)が高い項目は優先的に解く
・「用語とユーティリティ」の項目を落とさない
こうすることで「出る問題」に集中でき、効率的に得点源を押さえられます。



※参照元:LPIC-1 Exam 公式シラバス
解説を活用し、重要ポイントをメモ
学習初期は、解けない問題が多くても気にする必要はありません。まずは 解説を読んで理解を深め、重要部分をメモする ことが大切です。
■Ping-tの活用方法:
・ノートや単語帳に書き出す
・スマホでスクショを撮って復習する
・「重要ポイントを自分でまとめる」、「検索して調べた解説」を残す
これを繰り返すことで、知識が徐々に積み重なり、正答率が上がっていきます。



コマ問(記述問題)の対策
LPIC-1の試験では、入力式の「コマ問(コマンド問題)」が1割強ほど出題されます。
重要なコマンドやパスを入力する形式ですが、ここに時間をかけすぎる必要はありません。
■コマ問(記述問題)の対策:
・時間がある人 → Ping-tでコマ問対策を実施
・時間がない人 → 最小限の対策にとどめる(シラバスの「用語とユーティリティ」を覚える)
効率を重視すれば、Ping-tでコマ問対策をしなくても十分合格可能です。以下はPing-tのコマ問の例です。



Ping-tにかけるべき時間の目安
アウトプットは学習全体の中心に置きましょう。目安としては 全学習時間の5~6割をPing-tに充てる とバランスが良いです。
■(例)LPIC101試験に、80時間をかける場合:
・参考書(インプット):20時間(2.5割)
・Ping-t(アウトプット):40時間(5割)
・白本(追い込み):20時間(2.5割)
Ping-tは「独学で合格を目指すなら、避けて通れない教材」です。
スクール利用者なら、カリキュラムに従えばOKです。一方で、独学者 → シラバスを軸にPing-tを活用すべきです。
この意識を持つだけで、効率よく確実に合格ラインに到達できます。
効率を最大限に追い求めるなら、「Ping-tで問題を解く → 間違えたら解説を読む → シラバスに戻り、範囲を確認する」。この流れで、頻出項目を早期につかむことができます。
| 試験科目 | 金額 |
| 101試験 | 無料 |
| 102試験(利用期間1ヶ月) | 2,640円 |
| 102試験(利用期間2ヶ月) | 3,300円 |
| 102試験(利用期間3ヶ月) | 3,960円 |
ステップ3:追い込み(白本)
Amazon:LPICレベル1スピードマスター問題集: Version5.0対応 101試験、102試験対応
LPIC-1合格を目指す最後の総仕上げに最適なのが、「LPICレベル1スピードマスター問題集(通称:白本)」 です。
Ping-tと並んで多くの受験者が利用しており、直前対策用として特に強くおすすめできる教材です。
白本の特徴と強み
白本の一番の強みは、的中率です。合格者の声でも「白本から2割以上出題された」という体験談が多く、Ping-tと併用することで精度の高い試験対策ができます。
■白本の特徴と強み:
・約500問を収録:本番レベルに近い問題が豊富
・的中率が高い:実際の試験でも見かける問題が多い
・模擬試験付き:巻末の模試で、直前期の総仕上げが可能
私の個人受験でも、白本から101・102試験ともに10問程度出題されており、本試験レベルの問題に慣れながら本試験対策を行うことができます。
使い方のコツ
ここでは白本の使い方のコツを説明していきます。
■白本の使い方のコツ:
・試験直前期に取り組む
→本試験より難易度が高いため、Ping-tで基礎を固めた後、試験直前に使うのがベスト。
・重要度★★★・★★を優先
→全問に取り組む必要はありません。出題頻度が高い問題(特に重要度★★★)に絞ることで、効率的に仕上げられます。
・模擬試験で仕上げ
→巻末の模擬試験は、本番に近いレベル感かつ的中率も高い。時間を計って解けば、本番のシミュレーションになります。
・Ping-tとの違い
→Ping-tは網羅的、白本は本試験に近い問題で直前対策に強い、と覚えておきましょう。
学習効果の目安
白本を5~6割以上得点できれば、試験合格圏内と考えてもよいです。また、Ping-tと組み合わせることで、試験範囲の「抜け漏れ」を補完できます。
特に101試験対策で効果を発揮しやすく、試験直前期の安心材料となります。
→関連記事:【Linuxコマンド一覧】LPIC level1に出る、初心者向け基本まとめ
学習を効率化したい方へ|無料のリスキリングプログラムも活用可能です
「LPICを取って転職したいけど、独学では不安、、」
「教材費や受験料が高い、なるべく安く抑えたい、、」
そんな方は、学習サポートつきのリスキリング転職支援プログラムもご利用いただけます。
無料でLPIC-1が学べるリスキリング転職支援プログラム
- 教材・サポート費用:無料
- LPIC受験料:20%OFF+転職決定で全額キャッシュバック
- 転職支援まで一貫サポート
効率的に勉強を進めるためのコツ
LPIC-1は出題範囲が広いため、ただ参考書を読むだけでは効率が悪く、途中で挫折してしまう人も多いです。
ここでは、合格者が実践している「効率的に学習を進めるための3つのコツ」を紹介します。
間違えた問題を徹底的に復習する
合格への一番の近道は「できない問題を、できるようにすること」です。
■復習重視がおすすめ:
・1回目で正解できなくても気にしない
・解説を読み、なぜ間違えたのかを理解する
・苦手問題だけを繰り返し解いて、定着させる
LPICの効率的な合格には、弱点のつぶしこみが欠かせません。復習で弱点を克服しましょう。
学習スケジュールを逆算して立てる
LPIC-1は 「計画的に進められるかどうか」 で、効率的に進むか否かが分かれます。
■学習計画の目安:
・未経験者なら合格まで 130〜180時間 が目安
・例:1日2時間なら2〜3か月、1日1時間なら4〜6か月
「1か月後に101試験合格」といった明確な目標日を設定し、逆算でスケジュールを立てることで、ダラダラ勉強を防げます。
とにかくアウトプットする
LPICの勉強で多い失敗は「インプットが完璧になるまで、問題演習を避ける」ことです。しかし実際は、早い段階からアウトプットに取り組むほうが圧倒的に効率的です。
■アウトプットが最優先:
・参考書(インプット)は、ざっと読むだけで先に進む
・わからなくても、Ping-tを解いてみる
・間違えたら解説を読んで、シラバス範囲を確認する
この繰り返しで「点の知識」が「線」としてつながり、理解が深まります。完璧を目指すより、手を動かすことが最大の近道です。
この3つを意識すれば、同じ教材を使っていても「合格までのスピード」が大きく変わります。
【公開】LPIC-1合格までの勉強時間とロードマップ
「LPIC-1の勉強、どれくらい時間がかかるんだろう、、」と不安に思っていませんか?
ここでは、Linuxの知識ゼロから1ヶ月(合計100時間)でLPIC-1に合格した私の実体験をお伝えします。
実際にストップウォッチで計測し、記録した結果がこちらです。
| 勉強時間 | 勉強日数 | 点数 | |
| LPIC101試験 | 50時間 | 14日間 | 720/800点 |
| LPIC102試験 | 44時間 | 12日間 | 590/800点 |
LPIC-1は、今まで説明した内容でも合格できますが、おすすめできる勉強サイトも知りたいという方に向けて、下記より勉強サイトも説明していきます。
■関連記事:LPIC-101とは?出題範囲・難易度・勉強法を徹底解説
■関連記事:LPIC-102とは?出題範囲・難易度・勉強法を徹底解説
LPIC-1の学習をさらに効率化するコンテンツ
LPIC-1の学習にあたり、有料教材だけでなく、無料で利用できる勉強サイトや、実際にLinuxを触れる実機学習の方法も取り入れると、理解が一層深まります。
LPIC-1のおすすめ勉強サイト
LPIC-1の勉強には参考書や問題集が定番ですが、勉強サイトを併用すると効率が高まります。
特に無料で使えるサイトもあるので、コストを抑えながら学習を進めたい方におすすめです。
■おすすめの勉強サイト:
・LinuCイージス(無料):LinuC試験用だがLPICでも利用可、空き時間に手軽に学習可。
・LPI公式テキスト(無料):PDFで利用可、独学者でも出題範囲を体系的に押さえられる。
→ LPIC-1 Exam 101、LPIC-1 Exam 102
※勉強サイトまとめはこちら→ LPICおすすめ勉強サイトまとめ
LPIC-1の勉強で、挫折しないための3つのポイント
LPIC-1の勉強は出題範囲が広く、途中で「続けるのがしんどい、、」と感じる人も少なくありません。ただし、合格した人の多くは 「挫折しない工夫」 を取り入れながら学習を続けています。
ここでは、特に意識しておきたい3つのポイントを紹介します。
■LPIC-1で挫折しないポイント:
・学習の期限と目標を決める
・完璧を目指さず、立ち止まらずに進む
・難しい問題は、捨てる勇気を持つ
挫折しないポイント①:学習の期限と目標を決める
LPIC-1は範囲が広いため、「いつまでに合格するか」 を決めずに学習すると、「ダラダラ学習」となり、途中でモチベーションが下がりやすいです。
「2か月後に101試験に合格する」、「毎週Ping-tを◯問解く」など、小さくても具体的な目標を設定することで、学習にリズムが生まれます。
逆に、目標を決めないままダラダラ勉強を続けてしまうと、進捗が見えず、気づけばやめているというのは典型的な挫折パターンです。
ゴールを明確にし、進捗を数値化して確認できるようにするのが、挫折防止の大きな鍵です。
挫折しないポイント②:完璧を目指さず、立ち止まらずに進む
初心者が陥りやすいのは「最初からすべて理解しないといけない」と思い込むことです。
特に「なぜそうなるのか?」にこだわりすぎて学習が止まり、前に進めなくなる人が少なくありません。
ですが、LPIC-1の学習では まず知識を「点」として覚えることを優先し、前に進んでください。わからない部分は一旦スキップし、後で見直せば大丈夫です。
「なぜそうなるのか?」は深く考えず、ひたすらインプットとアウトプットを繰り返すと、点と点がつながり、自然に理解が深まります。
挫折しないポイント③:難しい問題は、捨てる勇気を持つ
LPICは満点を取る試験ではありません。2/3程度(65%以上)を押さえれば、合格できる試験です。
難しい問題に時間をかけるよりも、基本問題を確実に解けるようにすることが効率的。
特に多くの受験者は 101試験で苦戦しますが、そこを乗り切れば理解が進んで、102で挫折する人はほとんどいません。
「まずは101を突破する」ことに集中し、合格に直結する部分へエネルギーを注ぐのが最短ルートです。
LPIC-1勉強法に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、LPIC-1の勉強法について受験者からよく寄せられる質問に答えていきます。
Q1:LPIC-1は独学でも合格できますか?
はい、独学でも十分合格可能です。
定番の勉強ステップは「参考書で基礎を理解する → Ping-tで反復演習を行う → 白本(スピードマスター問題集)で仕上げる」です。これが王道であり、未経験でも合格が狙える手順です。
Q2:Ping-tだけで合格できますか?
可能ではありますが、白本(スピードマスター問題集)併用を強くおすすめします。
Ping-tは解説が丁寧で、知識の確認・反復、理解を深めることにとても適しています。ただし、Ping-tの的中率は決して高いわけではありません。
そのため、Ping-tだけで挑戦すると、「合格はできても 効率が悪い」、「問題運が悪ければ落ちるリスク がある」というデメリットもあります。
白本を併用することで、出題傾向に近い問題を効率よく押さえられ、合格率を高めることができるため、安心して試験に臨めます。
Q3:白本(スピードマスター問題集)だけで合格できますか?
エンジニア経験者なら、白本だけで合格できる可能性もあります。しかし 未経験者の場合、白本だけでは基礎理解が不足し、不十分です。
白本は本試験に近い問題が多く収録されており、「実質的な過去問集」として非常に有効です。特に巻末の模擬試験は本番に近く、直前対策に最適です。
ただし、白本はあくまでアウトプット用の仕上げ教材。解説を読むだけでは基礎が固まらないため、参考書+Ping-tと組み合わせるのが王道です。
Ping-tと白本をまとめると、「Ping-tだけ=合格できるが非効率」、「白本だけ=経験者なら可、未経験は不可」、「最短合格=Ping-t & 白本」です
Q4:LPIC-1と他資格(CCNA/基本情報)はどっちがおすすめ?
目指すキャリアによって変わります。
■資格の選び方:
・ネットワーク領域を目指す → CCNAがおすすめ
・サーバー・クラウド分野でキャリアを築きたい → LPIC-1がおすすめ
・幅広くIT基礎を押さえたい、開発職志望 → 基本情報がおすすめ
・インフラ全般に興味がある/まだ方向性を決めきれない → CCNAもLPIC-1も両方取るのがおすすめ
特にインフラエンジニアを幅広く目指す場合、「LPIC-1+CCNA」のセット取得は鉄板ルートです。どちらを先に取るかは、興味の分野で決めてOKです。
詳しくはこちら → LPICとCCNAはどっちを取るべき?比較解説
Q5:最初から実機環境を作らないとダメですか?
いいえ、最初から実機環境を作る必要はありません。
まずは参考書や問題集で基礎を固め、Ping-tなどでアウトプットを繰り返すだけで合格可能です。
余裕が出てきた段階で、VirtualBoxなどを使った実機環境に触れると理解がさらに深まります。
実機学習の流れはこちら → 初心者向け、Linuxの実機環境学習
結局どの勉強法で進めればよいか迷う、、
という方は、無料キャリア相談で最適な学習計画を一緒に立てることもできます。
LPICは「意味ない」のか?役に立つのはどんな人?
「LPICは意味がない」と言われることがあります。これは、実務経験が重視されるインフラエンジニアの世界では、資格だけで評価されるわけではないためです。
特に、すでに設計・構築経験が豊富なエンジニアにとっては、LPICは不要だと感じるでしょう。
しかし、LPICは以下の人にとっては、大きな意味と価値を持つ有効な資格です。
■LPICが役に立つ人の特徴:
・未経験からIT業界への転職を目指す人:
→LPICは、Linuxの基礎スキルを客観的に証明する最初のステップとして非常に有効です。資格があることで、未経験でも企業からの評価が高まります。
・運用・保守・監視からキャリアアップしたい人:
→LPICは、Linuxの基礎知識を体系的に学ぶことで、上位の構築ポジションへスムーズに移行する助けになります。キャリアアップや年収アップにもつながりやすいです。
LPICが意味ないと言われる理由はこちら →LPIC(LinuC)が意味ないと言われる理由とメリットまとめ
LPIC-1取得後のキャリア
LPIC-1はLinuxの基礎スキルを客観的に証明できる資格です。合格がゴールではなく、「資格をどう活かすか」 が大切なポイントになります。
ここでは、LPIC-1取得後に広がるキャリアの選択肢や、次に目指すべき資格、年収・キャリア形成への効果を整理していきます。
未経験からエンジニア転職に活かせる
未経験からインフラエンジニアを目指す場合、LPIC-1は履歴書や面接で強い武器になります。
■未経験転職でのメリット:
・採用担当者に「Linux基礎を理解している」と伝えられる
・監視オペレーター・運用保守など、エントリー求人に応募しやすくなる
・クラウドやサーバー構築へのステップアップの土台になる
ただし、資格だけで即戦力とは見なされにくいため、「学習意欲+資格」 をセットでアピールすることが重要です。
また、Linuxの知識が最も直接的に活かせるのは「サーバーエンジニア」です。内定を勝ち取るための具体的な転職戦略は、以下の記事で詳しく解説しています。
→関連記事:未経験からサーバーエンジニアになるには?仕事内容・資格・年収・ロードマップ
LPIC-1後におすすめの資格(CCNA/AWSなど)
LPIC-1を取得した後は、他のインフラ系資格を組み合わせることでキャリアの幅が広がります。
■LPIC-1取得後のおすすめ資格:
・CCNA:ネットワークの基礎を体系的に学べる。インフラ全体を理解するのに有効。
・AWS認定(SAAなど):クラウドスキルを証明でき、将来性の高いキャリアにつながる。
・LPIC-2:Linuxサーバーの構築・運用スキルをさらに高め、評価されやすくなる。
「サーバー・クラウド寄りならLPIC → AWS」、「ネットワーク寄りならCCNA」というふうに、キャリア志向に合わせて次の資格を選ぶのがおすすめです。
インフラエンジニアの全体像はこちらで解説 → インフラエンジニアとは?仕事・年収情報まとめ
資格についてはこちらで解説しています →インフラエンジニア資格ロードマップと学習順番
また、複数の資格をどう組み合わせて「最強のキャリア」を作るかについて、インフラエンジニアとしての全体像と、失敗しない進み方はこちらをチェックしてください。
→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?失敗しないルート選びと企業選び
資格取得が年収アップやキャリア形成に与える効果
資格はあくまでスタート地点ですが、経験と組み合わせることで大きなキャリア効果を発揮します。
■資格取得のメリット:
・年収アップのきっかけ
→例:未経験からLPIC-1で運用職に就職 → LPIC-2やAWS資格を追加 → 年収50万円以上アップも珍しくない。
・キャリアチェンジの推進力
→監視中心の業務から構築・運用へ、オンプレからクラウドエンジニアへ、といったキャリア転換に役立つ。
・「継続的に学べる人材」と評価される
→ 資格取得の姿勢自体が、採用や現場での評価につながる。
詳しいキャリアの流れはこちら → インフラエンジニアのキャリアパスまとめ
年収データの詳細はこちら → インフラエンジニアの年収比較記事
LPIC-1をキャリアにつなげたい方へ
当社の リスキリング転職支援プログラム なら、
経済産業省認定プログラムとして、無料で学習+資格取得+転職支援 が受けられます。
- LPIC受験料 20%OFF+転職成功で全額キャッシュバック
- 学習中の専属メンター・キャリア相談つき
- 未経験からインフラエンジニアへ最短ルートで転職
LPIC-1は、インフラエンジニアとしての基礎力を身につけるうえで重要な資格です。一方で、キャリア全体で見ると「Linuxの次に何を学ぶべきか」、「どこまでを基礎と考えるか」を早めに整理しておくことも大切です。
LPIC-1を含めたインフラエンジニア全体の勉強順や、ネットワーク・クラウドまで含めた全体像を整理したい方は、以下の記事も参考にしてください。
→関連記事:インフラエンジニアの勉強方法と順番|未経験からの独学ロードマップ
まとめ:LPIC-1独学は正しいステップで効率的に
LPIC-1は出題範囲が広く、一見ハードルが高そうに見えます。
ですが、この記事で紹介したように 「インプット → アウトプット → 追い込み」 の王道ステップを踏めば、未経験からでも独学で十分に合格が狙えます。
■LPIC-1学習で大事なこと:
・参考書(あずき本)で基礎を押さえる
・Ping-tで反復し、シラバスと照合しながら効率化
・白本(スピードマスター問題集)で直前期に仕上げる
・挫折しない工夫(目標設定/完璧を目指さない/難問を捨てる)
この流れを意識することで、最短ルートでの合格が見えてきます。
そして資格取得はゴールではなく、キャリアアップのスタート地点。「資格をどう活かすか」を考えることで、Linuxスキルを強みに転職や年収アップにつなげることができます。
■あわせて読みたい
→ LPIC-1とは?試験範囲・難易度・勉強法を徹底解説
→ 【Linuxコマンド一覧】LPIC level1に出る、初心者向け基本まとめ
→ CCNAとLPICを徹底比較、どっちを取るべき?難易度と順番を解説
→ 【まとめ】インフラエンジニアとは?未経験からわかる仕事内容・年収・キャリアパス
→ LPIC(LinuC)は転職で有利?資格のメリットと注意点、成功戦略を解説
「LPICを学びながらキャリアアップしたい」方へ
リスキリング転職支援プログラム なら、以下特典つきです。
■リスキリング転職支援プログラムの参加特典:
・無料で教材を利用できる
・LPIC受験バウチャーが20%割引
・当社経由で転職が決まった場合は、お祝い金として資格費用をサポート
・転職支援まで一貫サポート
→リスキリング転職支援の詳細はこちら
「今すぐ転職活動を始めたい」、「キャリア相談だけしたい」方へ
通常の無料転職相談もご利用いただけます。