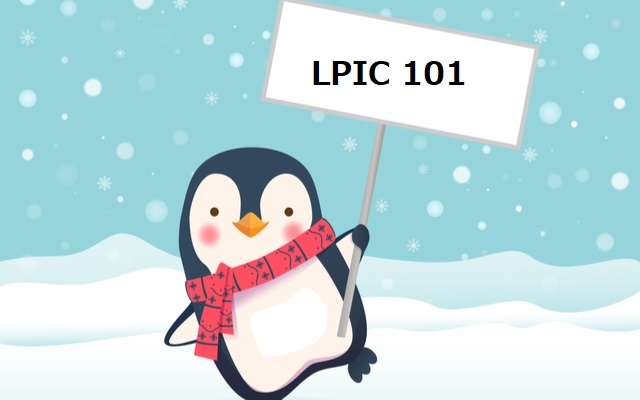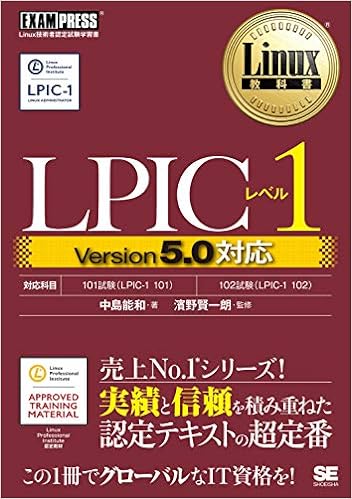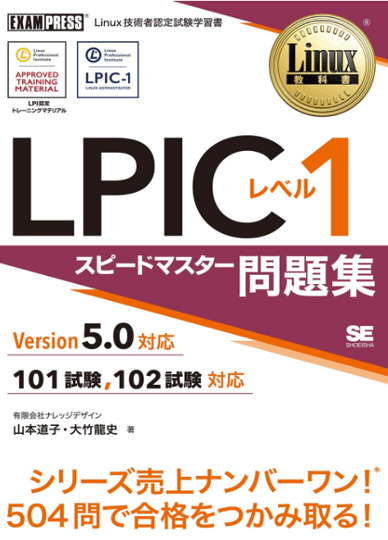こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。
「LPIC-101ってどんな試験?」、「未経験でも合格できるの?」、、Linux学習を始めたばかりの方は、こんな疑問を持つことが多いはずです。
結論から言うと、LPIC-101は未経験からインフラエンジニアを目指す第一歩として最適な資格です。
Linuxの基本操作からシステムアーキテクチャ、ファイルシステム、パッケージ管理まで、エンジニアとして必須の知識を体系的に身につけられます。
さらに、クラウドエンジニアへのキャリアアップにつながる基礎資格として、転職市場での評価も高いのが特徴です。
この記事では、LPIC-3認定取得/LPI公式トレーニングパートナー プラチナ認定企業の代表である筆者が、以下をわかりやすく解説します。
■この記事でわかること:
・LPIC-101の出題範囲と難易度
・合格率や学習時間の目安
・効率的な勉強法とおすすめ教材
・LPIC-102やCCNAとの違い
・資格取得後のキャリアと転職への活かし方
資格取得を通じて、インフラエンジニアとしてのキャリアを大きく前進させましょう。
※本記事は、LPI公式が公開している LPIC-101 Exam Objectives v5.0 に基づいて作成しています。2025年時点の情報です。
また、LPICの全体像を知りたい方は、以下記事も参考になります。
→関連記事:LPICとは?資格の種類・難易度・勉強法・申し込みまで徹底解説
→関連記事:LPIC-1とは?試験範囲・難易度・勉強法を徹底解説【初心者・未経験者必見】
LPIC-101とは何か?
LPIC-101は、Linux技術者認定試験(LPIC)の最初のステップとして位置づけられる試験です。
Linuxの基本操作からシステム構造、ファイル管理まで、エンジニアとして必要な基礎知識を幅広くカバーしており、未経験からインフラエンジニアを目指す人にとって最初の関門となります。
LPIC(Linux技術者認定試験)の概要
LPIC(Linux Professional Institute Certification)は、世界中で認知されているLinux技術者のための認定資格です。
運営しているのは、カナダに本部を置く LPI(Linux Professional Institute) で、グローバルで通用するLinux資格として評価されています。
特に日本国内では、インフラエンジニアやサーバーエンジニアを目指す方の登竜門として人気があり、求人票に「LPIC歓迎」と明記されているケースも多く見られます。
LPICの試験はレベルごとに分かれており、初級レベルの「LPIC-1」、中級レベルの「LPIC-2」、そして高度なシステム設計・セキュリティ・仮想化を扱う「LPIC-3」まで段階的にステップアップできます。
LPIC-1(101/102)の位置づけ
LPIC-1は「Linuxの基礎力を証明する」ための資格で、101試験と102試験の2つに合格することで認定されます。
101試験の位置づけ
主にシステムアーキテクチャ、Linuxインストールとパッケージ管理、GNU/Unixコマンド、デバイス・ファイルシステムといった OSの基礎構造や操作 が出題されます。
102試験の位置づけ
シェルスクリプト、ネットワークの基礎、セキュリティ、ユーザー管理など 運用寄りの知識 が問われます。
つまり、101は「Linuxを理解するための第一歩」であり、102は「Linuxを業務で使いこなすための知識」という位置づけです。
この2つをクリアすることで、Linuxサーバーの基本操作や運用の基礎知識を持つことが、国際的に証明されます。
101試験で身につくスキルと評価されるポイント
LPIC-101に合格することで、以下のようなスキルが証明されます。
■LPIC101試験で証明できるスキル:
・Linuxサーバーの基礎知識:ハードウェア構成、ブートプロセスの理解
・パッケージ管理の知識:dpkgやrpm、リポジトリ管理
・基本コマンド操作:ls、cp、mv、grep、findなど業務必須のコマンド
・ファイルシステムの管理:パーティション、マウント、FHS(Filesystem Hierarchy Standard)の理解
これらのスキルは、インフラエンジニアやサーバーエンジニアとして最初に求められる知識です。
特に未経験からキャリアを目指す方にとっては、「Linux環境を扱える基礎力がある」ことを客観的に示せる資格として、転職市場での評価を高める効果があります。
筆者自身もLPIC-3まで取得し、LPI公式トレーニングパートナーとして多くの学習者を支援してきましたが、未経験の方が最初に学ぶべき資格として、LPIC-101は非常に有効だと実感しています。
→関連記事:インフラエンジニアとは?未経験からわかる仕事内容・年収・キャリアパス
→関連記事:サーバーエンジニアとは?仕事内容・必要スキル・資格・将来性を徹底解説
LPIC-101の出題範囲
LPIC-101はLinuxの基礎力を問う試験で、大きく4つの分野からまんべんなく出題されます。
ただし各分野には出題比率が定められているため、効率的に合格を目指すには比率の高い分野を優先して学習することも重要です。
以下は、2025年時点での最新出題範囲です。
LPIC-101 出題範囲一覧
LPIC-101は、システムアーキテクチャからコマンド操作まで幅広い知識を問う試験です。特に出題比率の高い分野を把握することで、合格に直結する学習計画を立てやすくなります。
以下の表で、最新の出題範囲と比率を確認しましょう。
| 出題範囲 | 出題比率(目安) | 学習ポイント |
| システムアーキテクチャ | 約13% | ハードウェア設定、BIOS/UEFI、ブートプロセス、ランレベル(systemd)の理解 |
| Linuxインストールとパッケージ管理 | 約20% | Debian系(dpkg)、RedHat系(rpm)、リポジトリ設定、依存関係の解決 |
| GNU/Unixコマンド | 約43% | ファイル操作コマンド(ls、cp、mv)、テキスト処理(grep、sed)、プロセス管理(ps、kill) |
| デバイス・ファイルシステム・FHS | 約24% | パーティション、ファイルシステム作成(mkfs)、マウント/アンマウント、FHS準拠のディレクトリ構造 |
特に「GNU/Unixコマンド」のセクションは比重が高めであるため、このセクションを安定して70%以上正答できることが安定合格のポイントとも言えます。
最新の出題範囲は、LPIC公式サイトのLPIC-1 Exam 101 and 102 Objectivesで確認ができます。
出題範囲から見る学習のポイント
LPIC-101の合格には、出題範囲をただ暗記するだけではなく、比率や特徴に応じて学習の優先度を決めることが欠かせません。
以下では、出題範囲ごとにどのように勉強を進めるべきか、そのコツを解説します。
■出題範囲から見る、学習のポイント:
・システムアーキテクチャは基礎理解の要:
→CPUの動作モードやブートプロセスを理解することで、トラブルシューティングや起動時の問題対応に強くなる。
・インストール・パッケージ管理は頻出:
→実務でも必須なので、仮想環境で実際に操作しながら学ぶのが効果的です。
・GNU/Unixコマンドが最重要:
→全体の約4割を占めるため、コマンド操作に慣れることが合格のカギ。試験では、単一のコマンドのみでなく、複数のコマンドをパイプ(|)で組み合わせる実践的な出題もあります。
・ファイルシステムの理解は応用力につながる:
→マウントや権限設定をしっかり押さえることで、LPIC-102やクラウド学習にもスムーズに進める。
コマンド操作に慣れるためには、「手を動かす」ことが一番の近道です。
初心者の方は、仮想環境(VirtualBoxにLinuxをインストール)を使って、定番コマンド(例:ls、cd、cp、mvなど)を入力してみることから始めるのがおすすめです。
慣れてきたら、権限設定の基本コマンド(chmod、chownなど)にも挑戦すると、実務に直結する力が身についていきます。
難易度・合格率・学習時間の目安
「LPIC-101は難しいの?」、「合格率はどのくらい?」、「何時間くらい勉強すればいい?」、、これは受験を考える多くの人が気になるポイントです。
ここでは、難易度・合格率・学習時間の目安をまとめ、学習計画を立てやすくします。
合格点・問題数・試験時間
LPIC-101試験は、約60問の多肢選択式/記述式問題(通称:コマ門)が出題され、90分間で解答します。
合格ラインは 約65〜70%(試験ごとに変動あり) とされており、単なる暗記ではなく、実際にLinuxを操作して理解していないと解けない問題も一部含まれます。
合格率の実態と未経験者のハードル
公表されている公式の合格率はありません。しかし、受験者の声や教育機関のデータを参考にすると、以下程度と推測されます。
■合格率の実態:
・IT経験者/Linux経験者:合格率は70〜80%前後
・完全未経験者:初回合格率は50%前後
特に未経験者の場合は「コマンドを覚えたつもりでも、実行イメージが伴っていない」ことが不合格の原因になりやすいです。
学習時間の目安(未経験/経験者別)
学習時間の目安は、経験や学習スタイルによっても変わります。以下を目安とするとよいでしょう。
| タイプ | 学習時間の目安 | 学習のポイント |
| 完全未経験者 | 130-180時間 | Linux基礎から始め、仮想環境で実機操作をしながら学ぶ必要がある |
| IT経験あり | 50-100時間 | 重点的にLinux特有のコマンドとパッケージ管理を学習 |
| Linux経験あり | 30-50時間 | 出題範囲の抜け漏れをチェックし、模擬試験対策を中心に学習 |
ポイントは、「実機を使って学んだかどうか」で学習効率が大きく変わるという点です。
例として、chmodコマンドを学ぶなら、実際にファイルを作成し、権限を変更して挙動の違いを確認するといった体感を伴う学習が、知識の定着につながります。
→関連記事:【徹底解説】LPICの難易度は?レベル別で、他のIT資格と比較解説
LPIC-101と102はどっちが難しい?
「LPIC-101」と「LPIC-102」のどちらが難しいのか?は、多くの受験者が気になるポイントです。
結論から言うと、101はLinuxの基礎を幅広く暗記する必要があり、102はネットワークやシェルスクリプトなど実務寄りの知識が求められる という違いがあります。
■101の特徴:
・ファイル管理、パッケージ管理、基本コマンドなど基礎を網羅
・出題範囲が広いため、暗記量が多い
・未経験者にとっては「とにかく覚えることが多い」と感じやすい
■102の特徴:
・ネットワーク(OSI参照モデル、IPv4/IPv6)、シェルスクリプト、ジョブスケジューリング、ログ管理など
・実務に近い内容が多く、基礎を押さえていないと理解しづらい
・「暗記よりも理解+実践」で得点しやすい
一般的には「101=暗記量で苦戦」、「102=実務的で取っつきにくい」という声が多く、感じ方は人それぞれです。
ただ、これまで多くの受験者を支援してきた実感としては、8割強の方が「101の方が難しい」と答えている のが現実です。
102試験の詳しい試験範囲や勉強法については、「LPIC-102とは?出題範囲・難易度・勉強法を徹底解説」でまとめていますので、あわせてご覧ください。
LPIC-101に合格するための勉強法
LPIC-101は、Linuxを初めて学ぶ方にとって最初のステップとなる試験です。効率的に学習を進めるためには、「独学の進め方」「教材の選び方」「実機演習」の3つを意識することが重要です。
ここでは、初心者がつまずきやすいポイントを踏まえた勉強法を解説します。
独学での3ステップ学習法
LPIC-101は独学でも十分に合格可能な試験です。ただし、テキストを読むだけでは合格は難しく、インプット → アウトプット → 模擬試験 の流れを意識することが大切です。
ここでは初心者でも実践しやすい3ステップを紹介します。
■独学での勉強ステップ:
・ステップ1:テキストで知識をインプット
・ステップ2:Web問題集でアウトプット
・ステップ3:模擬試験とコマ問対策で総仕上げ
ステップ1:テキストで知識をインプット
まずは出題範囲を体系的に学ぶために、定番テキストを一冊決めてインプットを進めましょう。
おすすめ教材は、LPI公式認定教科書である、Linux教科書 LPICレベル1(あずき本)もしくはLPIC レベル1教科書&問題集です。迷うようであれば、定番テキストである「あずき本」を選択するとよいです。
テキスト学習のポイントは「最初から完璧に理解しようとせず、全体像をつかむ」ことです。テキストは辞書のように繰り返し参照し、理解が浅い部分は付箋やマーカーでチェックしておきましょう。
ステップ2:Web問題集でアウトプット
インプット後はすぐに問題集でアウトプット練習をします。
Ping-t などのオンライン問題集は解説が詳しく、弱点克服に最適です。また。間違えた問題は必ず「なぜ間違えたのか」を振り返りましょう。
アウトプット学習では、「解ける問題を増やす」よりも「解けなかった問題を潰す」ことが合格率を高めるコツです。
ステップ3:模擬試験とコマ問対策で総仕上げ
学習の仕上げでは、模擬試験やコマ問対策を取り入れて本番形式に慣れておきましょう。
学習の仕上げにおいて、もっとも役に立つのは、スピードマスター問題集(特に巻末の模擬試験)です。本試験に難易度が非常に近しく、頻出問題が厳選されています。
また、Ping-tの模擬試験モードや、Udemyの模擬試験を活用しながら、90分の制限時間で解く習慣をつけましょう。
さらに、本試験でうっかりミス(スペルミス)をしやすいのがコマ問(コマンド問題)です。実際にLinux環境でコマンドを入力して、動作を確認しながら覚えることで、知識が定着しやすくなります。
上記の3ステップを通じて、得点が安定して75-80%を超えるようになり、コマ問にも手が慣れていれば、本番でも落ち着いて実力を発揮できます。
プロが選ぶ!おすすめ教材4選
LPIC-101に合格するためには、テキストで基礎を学びつつ、問題演習と実機練習を組み合わせるのが効果的です。特に以下の教材は多くの受験者に利用されており、初心者にもおすすめできます。
Ping-t:オンライン問題集

オンライン問題集として定番です。解説が丁寧で、間違えた問題の復習がしやすいため、弱点克服に最適です。毎日の学習習慣づけにも活用できます。
あずき本:定番の教科書
Amazon:あずき本(Linux教科書 LPICレベル1 )
入門者向けの定番テキスト。出題範囲を体系的に学べるので、最初の一冊として最もおすすめです。
白本:スピードマスター問題集
Amazon:白本(Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集)
スピードマスター問題集は、試験的中率が高い問題集です。難易度が高いので、Ping-tの後に活用すると非常に効果的です。
Udemy:動画学習



Udemyは動画形式で学習したい人向けです。LPIC-1については「模擬試験形式のコース」が中心で、体系的な講座は少ないものの、直前演習や弱点チェックには役立ちます。
これらを組み合わせることで、知識のインプット → 問題演習 → 実機練習 → 模擬試験 という学習サイクルを回しやすくなり、合格率が大幅に高まります。
実機演習も重要!環境構築のススメ
LPIC-101の学習で最も重要なのは、実際にLinuxを操作して体で覚えることです。テキストや問題集だけでは理解が曖昧になりやすいため、しっかりと実機環境での演習を取り入れましょう。
VirtualBox/VMwareで仮想環境を構築
VirtualBoxやVMware を使って、自分のPC上にLinux環境(UbuntuやCentOSなど)を構築します。環境を壊してもすぐ再構築できるため、初心者でも安心して練習可能です。
また、インストールから設定までの流れを体験することで、試験範囲の「システムアーキテクチャ」や「パッケージ管理」の理解が深まります。
AWS/GCPの無料枠でクラウド環境を体験
AWSやGCPの無料枠 を利用すれば、より実務に近いLinux環境を体験可能です。また、SSH接続でサーバーを操作する流れを学べるため、就職・転職後にも役立つスキルになります。
日常的なコマンド練習
毎日数分でも、ls、cp、grepなどの基本コマンドを繰り返し入力して習慣化しましょう。慣れてきたら、権限設定(chmod、chown) や パッケージ管理(dpkg、rpm) にも挑戦してみましょう。
問題集で出てきたコマンドは、「実機で動かして確認するクセ」をつけることが大事です。
こうした実機演習を並行することで、「知識として覚える」から「実務で使えるスキルとして定着する」学習に変わり、合格率も大きく高まります。
→関連記事:LPIC-1勉強法まとめ|未経験から合格する最短ロードマップ
LPIC-101と他資格との比較
LPIC-101はLinuxの基礎を証明できる資格ですが、学習者によっては「LinuCやCCNAとどう違うの?」「LPIC-102も必要?」と迷うことも多いです。
ここでは、代表的な資格との違いを整理し、学習の優先順位を明確にします。
LPIC-101 と LPIC-102(違いとつながり)
LPIC-1は101試験と102試験の2つで構成されています。それぞれの違いと、学習のつながりを理解しておくことも大切です。
■LPIC-101 と LPIC-102:
・LPIC-101:
→Linuxの基礎操作(インストール、パッケージ管理、コマンド、ファイルシステムなど)を中心に出題
・LPIC-102:シェルスクリプト、ネットワーク基礎、セキュリティ、ユーザー管理など「運用寄り」の知識が出題
また、LPIC-1として認定されるには 101と102の両方に合格する必要があります。101だけでは資格として成立しないため、計画的に102まで進めることが重要です。
LPIC と LinuC(どちらを取るべき?)
「LPICとLinuCの違いは?」、「どちらを取れば転職に有利?」、、こうした疑問を持つ方は多いです。
両資格はLinux技術を証明する資格という点では共通していますが、認定団体や出題範囲、評価されやすい場面に違いがあります。
■LPIC と LinuC:
・LPIC:
→世界標準のLinux資格。海外でも通用するため、外資系やグローバル企業を目指す人に有利。
・LinuC:
→日本のIT業界に特化した資格。クラウド時代を見据えて、仮想化・コンテナ(KVMやDockerなど)を含む出題範囲が特徴。
国内就職を目指すなら LinuC、汎用的かつグローバルでも通用する資格を求めるなら LPIC と覚えておくとわかりやすいです。
どちらもLinux基礎を体系的に学べる点は共通しており、キャリアの方向性に応じて選択しましょう。
→関連記事:LPICとLinuCはどっちがいい?選び方を徹底比較
LPIC と CCNA(キャリアの方向性で選ぶ)
「LPICとCCNAはどっちを取るべき?」、「未経験からならどちらが有利?」、、こうした疑問も、インフラ系資格の中でも多いテーマです。
サーバー系の基礎を学ぶLPICと、ネットワークに特化したCCNA、それぞれの違いを知ってキャリアの方向性を選びましょう。
■LPIC と CCNA:
・LPIC:
→サーバーやLinux OSに関する資格。システム管理やクラウド基盤構築に直結。
・CCNA:
→Cisco社が認定するネットワーク資格。ルーターやスイッチ、ネットワーク設計・運用の基礎に直結。
インフラエンジニアを目指す場合、「サーバー寄りならLPIC」、「ネットワーク寄りならCCNA」 が基本的な選び方です。
両方を取得できれば、サーバー・ネットワーク両面からトラブルシューティングが可能となり、クラウド時代に強いエンジニアとして評価されます。
→関連記事:CCNAとLPICを徹底比較、どっちを取るべき?難易度と順番を解説
LPIC-101取得後のキャリアとメリット
LPIC-101は、単なる資格試験ではなく、インフラエンジニアとしてのキャリアを切り拓く第一歩です。
ここでは、合格後に得られる具体的なメリットと、どのようなキャリアパスにつながるのかを解説します。
■LPIC-101取得後のキャリアとメリット:
・サーバー運用・構築エンジニアとしての第一歩
・AWSやクラウド資格へのステップアップ
・転職市場での評価(年収・求人動向)
サーバー運用・構築エンジニアとしての第一歩
LPIC-101に合格することで、Linuxサーバーの基本操作や、運用知識の基礎を証明できます。具体的には、以下のようなチャンスに恵まれることもあります。
■LPIC101で生まれるチャンス:
・運用・監視オペレーターからのキャリアアップ
・サーバーの設定変更や障害対応を任されるチャンスが増える
・中小企業では「Linuxサーバーを扱える人材」として評価されやすい
また、未経験からインフラエンジニアを目指す場合、採用担当者に「学習意欲と基礎力がある」と示す有力な証拠にもなります。
→関連記事:LPIC(LinuC)は転職で有利?資格のメリットと注意点、成功戦略を解説
→関連記事:未経験からインフラエンジニアになるには?後悔しない学習・資格・転職ステップ
AWSやクラウド資格へのステップアップ
近年のインフラエンジニアにはクラウドスキルが必須です。特にAWS・Azure・GCPの学習を見据えている方にとって、LPIC-101は土台作りに最適です。
■LPIC101から始まるステップアップ:
・LPIC-101でLinuxの基礎を固めることで、AWS SAAなどクラウド系資格の学習がスムーズに
・実際のクラウド環境でも、Linuxコマンドや権限管理の知識を活用できる
・「オンプレ×クラウド」の両方を理解できるエンジニアとして市場価値が高まる
→関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容・資格・年収・将来性を徹底解説
→関連記事:インフラエンジニアがAWSを学ぶべき理由と勉強法、未経験からのクラウド転職
転職市場での評価(年収・求人動向)
IT求人では「Linuxの基礎知識を持っている人材」が常に求められています。
■転職市場での評価:
・LPIC-1(101+102)を取得すると、未経験可の求人だけでなく、サーバー運用・構築案件にも応募できる幅が広がる
・転職市場では「Linuxに触れたことがある」よりも、「資格で証明」が高く評価される
・結果として、年収アップやキャリアの選択肢拡大につながる
筆者(LPIC-3保持者/LPIトレーニングパートナープラチナ認定企業代表)の転職支援経験からも、LPICを取得した未経験者がサーバー運用・構築エンジニアとして転職成功する事例は多く見られます。
→関連記事:インフラエンジニアの年収相場まとめ【未経験〜経験者・年代別】
→関連記事:インフラエンジニアの将来性はある?AI時代の需要・キャリアを徹底解説
LPIC合格をキャリアにつなげるには?
LPIC-101に合格することはゴールではなく、キャリア形成のスタートラインです。資格をどう活かすかによって、その後の成長スピードや年収の伸びが大きく変わります。
ここでは、合格後に取るべき行動と、キャリアにつなげるための具体策を紹介します。
資格だけでなく「実務経験」が重要な理由
企業が重視するのは「資格」そのものよりも、資格で学んだ知識を実務に活かせるかどうかです。
LPIC-101で学んだコマンド操作やファイルシステムの知識は、運用現場で即戦力となりやすいです。ただし、資格だけで実務経験がゼロだと「知識止まり」と評価されることもあります。
だからこそ、資格取得後は現場経験を積む環境に早く飛び込むことが大切です。
効率的に経験を積める環境の探し方
「LPICに受かったけれど、どんな仕事から始めればいい?」、「未経験からどんな企業に応募すればいい?」――こうした悩みを持つ方は多いです。
ここでは、効率的に経験を積み、キャリアを前に進めるための環境の選び方を解説します。
■経験を積める環境の探し方:
・未経験歓迎のサーバー運用・監視求人からキャリアをスタート
・研修制度が整った企業を選べば、資格知識を早く実務に結びつけられる
・転職支援サービスやエージェントを活用し、学習内容をアピールできる求人を見つける
「資格を持っている=やる気と基礎力がある」と伝えられるため、転職活動での評価は確実に上がります。
未経験から最短でインフラエンジニアを目指す方法
LPIC-1の学習を終えた時は、キャリアを動かす最高のタイミングです。
Linuxの基礎を身につけた状態で、実務経験を積み始めることで、インフラエンジニアへの最短ルートを歩めます。
当社のリスキリング転職サービスでは、最短1.5カ月でLPIC-1(101・102)に合格し、インフラエンジニアに転職が決まった事例もあります。
また、当社はLPI公式トレーニングパートナーとして、教材・学習サポート・転職支援を一貫して提供しています。
もちろん、すべての方が同じスピードで進むわけではありませんが、「体系的な学習+伴走サポート+実務を意識した転職活動」を組み合わせることで、独学よりも早く、安定的にキャリアを築けるのが最大の特徴です。
一方で、「資格の活かし方」や「おすすめの求人」などを相談したい方は、無料キャリア相談からご相談ください。あなたに合ったキャリアや求人を、プロが提案します。
LPICを「学んで終わり」にせず、「キャリアの武器」にする。今行動できるかどうかが、1年後のキャリアを変えていきます。
\ LPIC取得をきっかけに、キャリアを変えたい方へ /
資格を取るだけで終わりではなく、「実務経験につながる環境」に飛び込むことが大切です。
当社では、未経験からインフラエンジニアへ最短でキャリアチェンジできる2つのサポートを用意しています。
- ① インフラエンジニア リスキリング転職サービス
経産省リスキリング事業採択/LPI公式パートナー認定。
学習+転職を同時に支援し、LPIC受験バウチャー割引付き。 - ② 無料キャリア相談
「資格を取った後どう活かすか?」をプロが個別アドバイス。
今のスキルから転職可能性を具体的に診断します。